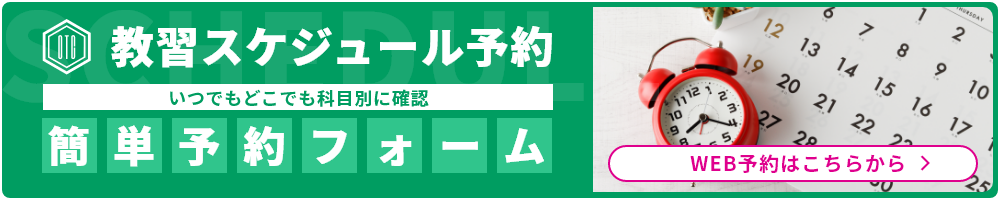玉掛け技能講習で習う基本的な掛け方6選を紹介!② | 岡山トレーニングセンター
2025.04.05

玉掛け技能講習で習う基本的な掛け方6選を紹介!②
前回のコラムに引き続き、玉掛け技能講習で習う基本的な掛け方を当コラムで解説していきたいと思います。
まだ①のコラムを読んでない方は是非、そちらからお読みください!
◀前の記事を読む
『玉掛け技能講習で習う基本的な掛け方6選を紹介!①』
吊り方④ くくり吊り
次ご紹介する吊り方はくくり吊りです。
折り返した部分にアイを通して、ぎゅっと絞ります。

通常の絞りと違うところは、1本で2点吊りという形になる点です。
より安定しますが、2点吊りの中心がお互いに傷みやすくなります。
また、センターが少しでもずれると、すぐに傾きます。
さらに、曲がって折れているので通常の耐荷重よりもかなり減少しています。

くくり吊り1本でも2点吊りになりますが、くくり吊りをする場合でも、2本使用して吊った方がバランスが良いですね。
特に長物などの場合は2本使用して吊るようにしましょう。
ちなみに、くくり吊りには逆のやり方もあります。
折り返し部分をアイの部分に通して、折り返し部分をフックにかけます。

この状態で吊ってみると、吊り姿はまったく同じですが、違う点は、フックの部分が半掛け状態になっているところです。

くくり部分は半掛け状態の方が良いです。
なぜなら、半掛けだと自動的にセンターを捉えることができるからです。
一方で、下の写真のように、アイ側をフックに掛ける場合、左右の長さが均等でなければ、片方はテンションがかかり、片方は緩むことがあります。
アイの方をフックにかける場合は、必ず吊り上げる前に、玉掛け側のアイ位置の長さを均等に調整してから掛けてください。

このように2つに折って吊るケースとしては、建物内で上部に高さに制限があり、玉掛け用具を短く使いたい場合などに当てはまります。
吊り方⑤ 目通し吊り
続いて、目通し吊りです。
まず、荷物の下に吊り具を通して、アイの部分にもう片方の端を通します。
基本は2点吊りになるので、絞って左右均等の位置にします。

目通し吊りは絞りとも呼ばれます。
これは、吊り荷が絞られていることに由来しています。
荷が揺れても、絞られているので比較的バランスを崩さずに吊ることができます。
囲い込む、包み込むように玉掛け用具が回っているので、よりしっかりと吊り荷をホールドします。
ただ、段ボールや木箱など、中に空間があるものは、その部分が潰れてしまう恐れがあります。
中に空間のあるものには、この絞りを使うと破損する可能性があるため、用途を見極めて使うことが大切です。

ちなみに絞りにも種類があります。
荷物に隙間なくしっかりと絞られている状態を深絞りと言います。
荷物との間に隙間がある絞り方は、浅絞りと言います。
基本的に現場では隙間をなくす深絞りにします。
そうすることで、吊り荷が安定して固定されます。

一方で、浅絞りにも利点があり、荷物をあまり締め付けたくない場合には、あえて浅絞りにすることもあります。

注意点はワイヤーロープで絞る場合、ワイヤー自体が擦れ合って、吊り具が痛んでしまうことです。
そういった場合には、シャックルを使用します。
アイの片方にシャックルをつけ、ワイヤーをシャックルの中に入れ、ピンを止めます。
ワイヤー同士が直接触れ合わないように、シャックルを通して干渉しないようにします。
これによって、ワイヤーロープの寿命も延びます。

また、シャックルのボルト側をアイの方にします。
逆の場合、テンションをかけたり緩めたりする時に、ワイヤーが擦れてボルトが動きピンまで動く可能性があります。
そのため、必ず吊り荷側のボルト側はアイの方にしてください。

また、ワイヤーのアイがシャックルのボルト側にきていて、Uの方がフックに向いくような互い違いにすることで、地切りした時に荷物が回転しません。
同じ方向の場合は回転しやすくなるため、足場などでは同じ向きにしない方が良いです。
互い違いの方が回転しないので、そちらの方が良いと思います。

吊り方⑥ あや掛け
次は、あや掛けです。
今回はタイヤを吊っていきますが、一つずつなら、手で持ち上げることもできます。
しかし、5個、6個になると、持ち上げるのが難しくなってきます。
今回は、タイヤの束を吊ってみたいと思います。
まず、スリングをまず直線に伸ばします。
そして片方のスリングを十字に配置します。
次に90度ひねります。
さらに、もう片方も90度ひねり、互いが引っ張り合う形にします。

クロスした個所が中央になるように荷を置いていきます。
スリングを十字に配置して中央に据えることで、吊るすことができます。
それぞれのスリングが中央に寄ろうとするため、自然と真ん中に寄せ合う形になります。

会社情報
岡山トレーニングセンター
岡山市南区浦安南町243
TEL:086-241-0555
FAX:086-241-0556
受付:月~土(祝日含) 9:00~17:00
◤詳しいアクセス情報はこちら!◢
◤Webでのお問い合わせはこちら!◢
:::::::::::::::::::::
✅よくある質問を見る
✅取得できる資格一覧をチェックする
✅講習料金を知りたい
✅講習日程を知りたい