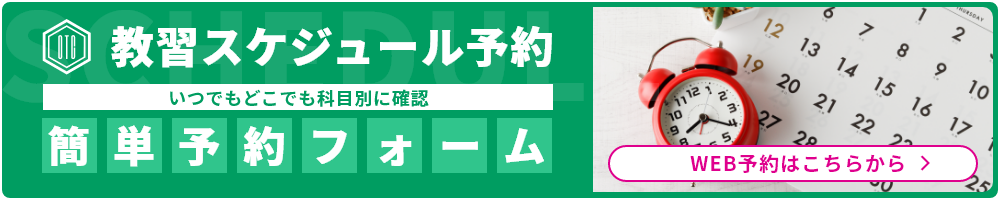トラック式高所作業車の完全ガイド:種類・特徴から安全な使い方、現場事例まで徹底解説 | 岡山トレーニングセンター

目次
トラック式高所作業車の完全ガイド:種類・特徴から安全な使い方、現場事例まで徹底解説
高所作業車の種類と分類
高所作業車は、地面を移動するための「走行装置(走り方)」と、作業床を昇降させる「作業装置(動き方)」の組み合わせで、様々な種類に分けられます。
・走行装置の種類
| 種類 | 特徴 |
| トラック式 | 公道を自走でき、機動力が高い。 |
| クローラ式 | キャタピラで不整地や軟弱な地盤に強い。 |
| ホイール式 | タイヤで走行し、整地された床面での作業に向いている。 |
・作業装置の種類
| 種類 | 特徴 |
| 屈折ブーム型(屈伸式) | ブームが関節のように折れ曲がり、障害物を避けて作業できる。 |
| 伸縮ブーム型 | ブームがまっすぐ伸び、直線的に対象へ接近できる。 |
| 垂直昇降型(シザース式など) | 作業床が真上に昇降し、安定性が高い。 |

本記事では、この中でも上の画像のような、走行装置が「トラック式」である高所作業車に焦点を当てて解説します。
▶▶▶各高所作業車の区分や特徴について詳しく知りたい方はこちらのコラムをチェック!!🤓👍
▶▶▶YouTube登録者数3万人突破✨現場で役立つ情報を発信しています!
トラック式高所作業車とは
トラック式高所作業車とは、トラックシャーシに高所作業装置(ブーム・バケットなど)を装備した車両です。
主に公道を自走できるため、現場への移動がスムーズで、設置や撤収の手間が少なく、都市部の電柱や街路灯の点検・工事に多く利用されています。
作業床の高さは10〜30メートル前後が一般的で、アウトリガー(車両を安定させる脚)を広げて安全に高所作業を行えます。
作業の効率化や安全性の観点から、電気通信工事会社や建設業者、自治体のインフラメンテナンス部門などで広く導入されているのが特徴です。
多くのモデルでは以下のような機能・性能を備えています。
- 12m、17m、27mなど多様な作業床高さ
- アウトリガーや水平維持装置による安定性確保
- 昇降中の安全停止装置、インターロック機構
※作業床の高さが10m以上の機種で作業装置を操作するには、「高所作業車運転技能講習」を修了する必要があります。
なお、公道を走行するには、その車両の総重量や最大積載量に応じた自動車運転免許(準中型、中型免許など)が別途必要です。
↓画像をクリックして解説動画をチェック!!🚙💫

⭐岡山トレーニングセンターでは高所作業車の技能講習を開講しております!!
↓5名以上の予約なら、団体スケジュールプランで一括予約が可能です!

トラック式高所作業車のメリット・デメリット
公道を走行できる機動力と、高所での作業能力を併せ持つトラック式高所作業車は、作業効率の向上や安全性の確保といった大きな期待が寄せられる一方で、その特性を十分に理解し、最適な機種を選定・運用することが重要です。
ここでは、トラック式高所作業車が持つ具体的な強みと、導入・運用時に考慮すべき点について、メリットとデメリットの両面から詳しく見ていきましょう。
メリット
- 公道を走行できるため、現場までの移動がスムーズで効率的。
- 機動性が高く、都市部の狭い道路や現場に適応しやすい。
- 現場間の移動が迅速なため、一日に複数の現場を回るような作業で時間を短縮できる。
- 多様な高さの機種が揃っており、用途に応じて選択可能。
デメリット
-
- 車両自体が大型のため、駐車スペースや作業スペースが制限されることがある。
- 車両重量が重く、狭くて弱い路面では使用が難しい。
- 運転および操作には専門の資格と高度な技能が必要。
- 定期的な点検やメンテナンスが不可欠で、コストがかかる。
トラック式高所作業車の実際の使用例と安全上の注意点
トラック式高所作業車の現場での使用例
トラック式高所作業車は、道路を自走できる機動力と高所作業機能を併せ持ち、特に都市部や公共インフラの整備・保守現場で多く使用されています。
作業対象は多岐にわたり、電気・通信設備の設置から橋梁の点検、道路照明の設置作業など、幅広い用途に対応可能です。
各現場の特性に合わせて機種選定を行うことで、作業効率と安全性の両立が図れます。
以下の表では、代表的な使用現場ごとに、作業の具体例と、適切なトラック式高所作業車を選定する際のポイントを整理しました。
| 使用現場 | 作業内容 | 機種選定のポイント |
| 通信インフラ工事 | 電柱や通信塔の設置・点検・メンテナンス | 12〜17m級の機種、 旋回機能と安定性重視 |
| 橋梁点検 | 橋の側面や下面の点検、塗装、補修作業 | 張出アームの可動範囲、 狭所対応型バケット |
| 道路照明設置 | 街灯・信号機の取り付け、ランプの交換 | コンパクトな17m級以下、 交通規制に対応 |
| トンネル内部作業 | 照明の設置・点検・清掃、換気装置の保守 | 低車高・短ボディタイプ、 高輝度作業灯搭載 |
使用にあたっての注意ポイントと危険回避策
トラック式高所作業車は非常に便利な作業機械ですが、操作を誤ると転倒や挟まれ事故など重大な災害を引き起こすリスクがあります。
事故を未然に防ぐには、機械の特性や作業環境を十分に理解し、安全対策を徹底することが求められます。
以下に、安全確保のために重要なポイントと、見落としがちな注意事項を含めた対策を整理しました。
| 注意点 | 具体的な対策・補足 | 見落としがちな点 |
|
事前点検の |
作業開始前に、ブーム、バケット、旋回装置、油圧系統、安全装置の作動確認を行う。 | タイヤやジャッキの空気圧、 油圧ホースの劣化、 非常停止スイッチの動作確認。 |
| 周囲環境の 確認 |
電線や木の枝、建築物との接触を避け、歩行者や車両の動線に注意する。 | 地面の傾斜や路面の強度 (アスファルトの沈下やマンホールの上)、風速の確認。 |
| オペレーターの資格と訓練 | 「高所作業車運転技能講習」の受講は必須。定期的な実地訓練や操作シミュレーションも効果的。 | 補助者や作業指揮者の訓練不足。 オペレーターだけでなく 周囲のスタッフ全体の意識も重要。 |
| 安全装置の 活用 |
傾斜センサー、過負荷警報、インターロック機構などの機能を理解し、正常に作動していることを確認。 | 警報音が鳴ったまま作業を続行する誤操作。 センサーの誤作動や故障時には使用を中止する。 |
| 作業中の 連携体制 |
作業員、指揮者、オペレーター間で明確な合図や無線機を使用した連絡体制を構築。 | 無線の電池切れや通信不能時の対応策を準備していないケース。 手信号のルールを共有しておく。 |
| 風や天候の 変化 |
作業中は風速計で常に風の強さを確認し、10m/s以上の風速では作業を中止する。 | 高所では地上より風が強くなるため、実際より安全と思い込まないこと。 |
| 緊急時の 対応訓練 |
落下、挟まれ、火災等の緊急時に備えた対応マニュアルを用意し、定期的に訓練を行う。 | 新人や派遣スタッフへの周知不足。緊急時対応ボタンの操作に不慣れなまま使用する。 |
| 積載荷重の厳守 | 作業床に定められた積載荷重(人、資機材の合計)を絶対に超えない。 過積載は転倒の直接的な原因となる。 |
「これくらいなら大丈夫」という安易な判断。 資材や工具の重さを正確に把握していない。 |
| 保護具の完全着用 | 保護帽はもちろんのこと、作業床では必ず墜落制止用器具(安全帯)を使用し、備え付けのフックに掛ける。 | 手すりに乗り出すなど、作業床から身を乗り出す危険行為。 フックの不使用や不適切な箇所への取り付け。 |
これらの対策を徹底することで、トラック式高所作業車の安全な運用が可能になります。
「慣れているから大丈夫」と過信せず、常に初心に立ち返って確認を行うことが、安全作業の基本です。
まとめ
高所作業車は種類ごとに特徴と適した作業環境が異なりますが、本記事では特にトラック式高所作業車に注目して解説しました。
トラック式は公道走行ができ、都市部のインフラ整備に強みを持つ機種で、機動力と多機能性が魅力です。
しかし、操作には専門の資格や技能が求められ、事前点検や安全確認の徹底が欠かせません。
現場に応じて適切な機種を選び、安全に配慮した運用を行うことが重要です。
高所作業の安全確保のため、資格取得や技能講習を通じて正しい知識と技術を身につけましょう。
岡山トレーニングセンターでは、高所作業車の運転技能講習を開講しています。
最低開催人数は5名以上となっていますので、詳しく知りたい方は問い合わせフォーム、またはお電話(086-238-0508)よりお問い合わせください!

↑5名以上の予約なら、団体スケジュールプランで一括予約が可能です!!!
YouTubeもやっています!✨
ユニック車に関する動画はこちら!!!
お役立ち動画を上げているので、ぜひチャンネル登録してください♪
会社情報
岡山トレーニングセンター
岡山市南区浦安南町243
TEL:086-238-0508
FAX:086-241-0556
受付:月~土(祝日含) 9:00~17:00
◤詳しいアクセス情報はこちら!◢
◤Webでのお問い合わせはこちら!◢
:::::::::::::::::::::::::::
✅よくある質問を見る
✅取得できる資格一覧をチェックする
✅講習料金を知りたい
✅講習日程を知りたい